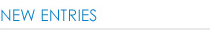文字サイズの変更
- 小
- 中
- 大
3月31日(火)参議院財政金融委員会において、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)について質問しました。
NACCSとは、税関手続き、その他の輸出入関連省庁の手続き、及びこれらと関係する民間業務を処理する官民共用のシステムのことです。
かつて輸出入関連手続きは、省庁ごとに別々に行う必要がありましたが、NACCSによって窓口の一元化とペーパーレス化が実現しました。
輸出入申告総件数の98%がNACCSを利用しており、日本の輸出商品としても海外から高い評価を受けております。
NACCSによって、窓口とデータベースの一元化は実現されましたが、省庁間の情報の共有は為されておりません。たとえば、農林水産省所管の植物検疫検査に引っかかった輸入品に関する情報については、港湾を管理する国土交通省の側からアクセスできません。
しかし、税関業務は多忙を極めており、情報共有による業務の効率化が考えられます。
また、NACCSを運営する輸出入・港湾関連情報処理センター(NACCSセンター)は、法律(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律)によって、できる限り速やかに株式を売却することが定められています。
しかし、NACCSで扱う情報の重要さに鑑みれば、いかにして情報セキュリティを図るかが問題となります。
そこで、以下の点について質問しました。
①省庁間の垣根を越えてNACCS登録情報の利用を認めるべきではないか。
②NACCSセンターの株式売却に当たり、いかにして情報セキュリティを図るのか。
①については、麻生財務大臣より、
「当該省庁の利用目的以外に利用を行わない、という前提で情報提供を受けている。そのため、他の行政機関による利用は許容されないことを、ご理解いただきたい。」とのご答弁をいただきました。
②について、財務省関税局長より
「株式売却後も、国が引き続き議決権の過半数を保有することが義務付けられている。」
「法律によってNACCSセンター職員に守秘義務が課されている。」
「業務運営について、財務大臣の認可・監督・報告の求めなど国の一定の関与が定められている。」とのご答弁をいただきました。
NACCSは重要なシステムと考えております。そのため、株式の売却方法や売却後の制度設計については慎重に考えて頂きたいと考えております。
3月31日(火)参議院財政金融委員会において、麻生金融担当大臣にジュニアNISA(J-NISA)についてお尋ねさせて頂きました。
NISAとは、年間100万円(今次法改正により120万円に拡張)の限度で行った投資から得られた利益(転売利益や配当金)について非課税となる制度のことです。(本来は20.315%が課税されます。)
現行NISAは20歳以上の方のみが利用できる制度となっていますが、これを20歳未満の方にも広げようというのが、ジュニアNISA(J-NISA)となります。
若年層への投資のすそ野の拡大という点については、私もかねてから必要と考え、NISAの投資可能年齢を18歳以上に引き下げるべきだと提言していました。
ただ、J-NISAでは、年齢の下限は設けられておりません。
投資のすそ野を広げるのであれば、投資判断を行える年齢が前提となるのではないでしょうか。
また、あまりに年齢が幼いと、子供や孫の名義で口座を開設しつつ、実際には親や祖父母が口座を管理する「名義口座」の問題が生じてまいります。
そこで、以下の点についてお尋ねさせて頂きました。
①J-NISAの年齢の下限を設けるべきではないか。
②いかにして名義口座とJ-NISAを区別するのか。
金融庁総括審議官から、
①について
「高齢者の方の資金ニーズの中には、子や孫に役立てたいというものがある。そのため、資産の移転という意味でも使える形で考えている。」
②について、
「窓口において、子供や孫本人のための口座であることを確認のうえ、口座開設を行うようにする。窓口でどのように対応するのかは、今後詰めていきたい。」
とのご答弁をいただきました。
しかし、本人のための口座確認を行うのであれば、本人を関与させるのが最も適切なのではないでしょうか。そのためにも、下限の年齢を設定する必要があるのではないでしょうか。
そこで、これらを指摘しつつ、麻生大臣へ、「名義口座との違いを明らかにするためにも、下限の年齢を設定して、本人の関与を求める制度設計にすべきではないでしょうか。」と提案させていただきました。
麻生大臣は、指摘に対して得心されたような表情で頷きつつ、提案に対しては、率直に「検討します。」とご答弁されました。
若年層へ投資のすそ野が広がるJ-NISAとなるように、麻生大臣のご判断を期待させて頂きます。
3月26日(木)財政金融委員会において、2%の物価安定目標に対する政府の認識を質問しました。
2月26日(木)財政金融委員会において、日本銀行黒田総裁から「できるだけ早期に2%の物価安定目標を目指す、というプライオリティに変わりない」とのご答弁をいただいております。
【参考】2/26(木)参議院 財政金融委員会 報告 http://nakanishikenji.jp/diet/14965
ところが、2月17日・18日の日銀政策決定会合議事要旨によると、2%の物価安定目標について、財務省の出席者も、従来の「できるだけ早期に」から「経済・物価情勢を踏まえつつ」に発言内容を変更していることが確認されます。
これまで、内閣府の月例経済報告のなかで「できるだけ早期に」という文言の削除は認められましたが、今回は、財務省が日銀の政策決定会合において、これと平仄を併せたことが伺われます。
そこで、以下の点を尋ねました。
①政府の方針は、すでに「2%の物価目標の達成を急ぐ必要はない」という方向に変更されているのではないか。
②仮に政府と日銀の方針にズレがないのであれば、改めて「できるだけ早期に」という文言を入れては如何か。
麻生財務大臣からは、以下のご答弁をいただきました。
①について
「足元の物価状況について、原油価格が下がっており、当面横ばいの圏内で推移すると考えているため、政府としては、1月の月例報告で『できるだけ早期に』を落とした。」
「財務省出席者の発言は、この立場を整合的に表現したものと考えている。」
「政府としては、日本銀行は物価安定目標の実現に向けて大胆な金融緩和を着実に実行していくことを期待しており、共同宣言の時から基本的なスタンスは変わっていない。」
②について
「共同宣言における『できるだけ早期に』という表現は、白川総裁(当時)との、5年は長すぎる、1年は無理だ、というやりとりの中で、まあ2~3年くらいかなということでまとまった。」
「改めて『できるだけ早期に』という表現を入れてしまうと、その表現が独り歩きしてしまうことを恐れている。」
とのご答弁をいただきました。
原油価格の低迷が物価安定目標に影響を及ぼす中で、慎重に言葉を選ばれているのだと痛感いたしました。
3月24日(火)参議院財政金融委員会において、麻生財務大臣へ、2020年度プライマリーバランス黒字化について質問させて頂きました。
政府は2020年度プライマリーバランス黒字化を目標に掲げていますが、2020年度プライマリーバランスの試算は赤字となっています。
しかし、2020年度プライマリーバランスの試算は、内閣府と財務省という2つの省庁から、異なる赤字額で出されています。
内閣府の試算は「中長期の経済財政に関する試算」であり、これによると国・地方の財政の姿として9.4兆円の赤字(国単体では9.1兆円の赤字)、財務省の試算は「後年度影響試算」であり、これによると国単体で8.0兆円の赤字となっています。
【内閣府】中長期の経済財政に関する試算
http://www5.cao.go.jp/keizai3/econome/h27chuuchouki2.pdf
【財務省】平成27年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
http://www.mof.go.jp/budget/topics/outlook/sy2702a.pdf
そこで、以下の点について質問しました。
①政府の公式見解として、どちらの試算を用いるのか。
②もう一つの試算の位置づけは、どういったものか。
③(内閣府の試算を公式見解とする場合)プライマリーバランス黒字化への不足額は、9.4兆円で動かない、ということか。
これに対する麻生財務大臣の答弁は以下の通りです。
①について
「一言で申し上げると、政府の公式見解は、内閣府の試算です。」
②について
「財務省の試算は、財務省としての公式見解です。」
「積算方法が違うというだけで、それ以外にさしたる意味はございません。」
③について
「出発点として9.4兆円でスタートさせます。」
国民の立場からすると、政府が目標する2020年度プライマリーバランス黒字化において、1兆円も異なる2つの数値がでており、それらがともに公式なものというのは理解を得にくいのではないかと考えます。
今後も、国民目線、ユーザー目線で、国の財政問題を追及して参ります。
参議院 財政金融委員会において、黒田東彦日本銀行総裁へ、物価安定目標を中心に質問させて頂きました。
【物価安定目標の早期達成】
政府の側から、「2年で2%の物価安定目標」について、柔軟に考えるように示唆する意見が散見されるようになりました。
そこで、黒田総裁へ「できるだけ早期に2%の物価安定目標を目指す、というプライオリティに変わりはないのか」を尋ねました。
黒田総裁からは、
「プライオリティは全く変わらない。」
「政府との共同宣言で示した『日本銀行は自らの判断と責任において2%の物価安定目標をできるだけ早期に実現する』というスタンスに変わりはない。」
とのご答弁を頂きました。
【オーバー・シュートのリスク】
足許でゼロ近辺まで低下した物価上昇率が1年程度で2%に達するとすれば、市場の感覚では「急上昇」ということになります。
そこで、2%を突き抜けて、3~4%にまで及ぶオーバー・シュートのリスクに対する黒田総裁の認識を尋ねました。
黒田総裁からは、
「2%で安定的に持続することを目指している。」
「どんどん上がっていくことを容認するつもりはない。上振れリスクが認められた場合は、必要に応じて躊躇なく調整を図る。」
「消費税増税の前後であっても、日銀は、日銀の判断として、躊躇なく調整を図る。」
とのご答弁を頂きました。
【出口戦略】
これまで日銀は「サプライズ」と言われるほど市場に先行してきましたが、一旦後手に回ってしまうとかえって市場が暴れることが懸念されます。
黒田総裁自身も、かつて「2015年度中に出口戦略について議論する」と仰っていました。
そこで、出口戦略の着手について尋ねました。
黒田総裁からは
「出口戦略は、出口に差し掛かった段階で当然議論しなければならない。ただし、米国の例をみても極めて慎重に行う必要がある。」
「出口戦略云々については内部的には議論を行っているが、政策委員会として何かを決めるのは時期尚早と考えている。」
とのご答弁を頂きました。