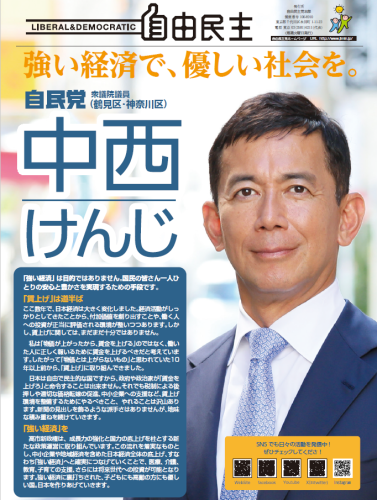

日本の人口は減少していますが、神奈川3区は成長を続けています。一方、高齢化は他の地域と同じように進んでいます。この大変難しい政策運営に対して、市、県、国が一体となって取り組んでいきます。#鶴見区 #神奈川区

「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と言われないように、しっかりと取り組んでいきます。
(鶴見区版 https://x.gd/9IhBy)
(神奈川区版 https://x.gd/X1YgL)
#鶴見区 #神奈川区
「どうして賃上げって必要なの?」とチコちゃんに聞かれて、「物価が上がったから」では「ボーっと生きてんじゃねーよ!」ですね。私は「物価は上がらないもの」と思われていた10年以上前から「賃上げ」を訴えてきました。
#鶴見区 #神奈川区.
+++++++++++++++++++
どうして賃上げって必要なの?
「ボーっと生きてんじゃねーよ!」
チコちゃんに叱られる!の有名なセリフですね。当たり前すぎて理由なんか考えたこともないことについて、改めて 「なぜ?」と問い直されるたびに、「えっ、なんでだっけ?」「確かに考えたことなかった、、、」と、私も答えに窮しています。
そこで「どうして賃上げって必要なの?」とチコちゃんに聞かれたらどう答えるのか考えてみました。
「過去最高益を上げた企業が、賃金を上げないのはおかしい。我が国の企業の労働分配率、つまり会社がもうけたお金のうち、どれくらいを従業員の給料として回しているかを示す割合は、世界的に見て低い状態が続いている。それを、さらに下げてしまうなどということは理解に苦しむ」と国会で取り上げたのは十年も前のことです。
それから何度も「賃上げを、、、」と言い続けてきたので、私にとっては当たり前すぎて、改めて理由を考えたことなどありませんでした。でも、答えに窮している場合ではないですね。
家計や生活の安定のため
すぐに思いつくのは、物価が上がっているのに賃金が上がらないと、買いたいものが買えなくなってしまうということです。
逆に、物価の上昇を上回る賃上げによって安心して暮らせるようになれば、多くの皆さんの気持ちが明るくなります。仕事に対する意欲が高まりますから、さらに頑張ろうという後押しになることは間違いありません。
ということで、答えは「皆さんの生活を守るためだから」になりました。
ただ、これではイマイチですね。「物価が上がったから賃金も上げる」というのでは、まったく後ろ向きです。物足りません。そんな経営者がいたら、本当に「ボーっと生きてんじゃねーよ!」です。
会社が生き残るため
経済活動が活発になってきたので、人手不足を訴える企業が増えました。ブラック企業が社会問題となった時代とは、完全に変わっています。
そんな中で人材を確保するには適切な報酬が不可欠ですから、賃金を上げるのは当たり前ですね。これは生産性の低いビジネスモデルからの転換を促すことにもなり、日本経済の体質の改善につながります。
更に付け加えると、日本の賃金は諸外国と比べて低くなってしまっています。高い付加価値を生む優秀な人材に正当な賃金を払わないと、「だったら、海外に行って働くよ」と言われかねません。人材の流出は、日本の成長力を殺いでしまいます。
そもそも、働く皆さんに対して払う賃金を、コストだと考えるのはおかしなことです。松下幸之助翁は「企業は人なり」と言う名言を残しました。企業は収益を上げるために設備投資や研究開発投資などを行ないますが、実は人材に対する投資が一番大切なものです。
従って、「賃上げは、会社が生き残るために重要な投資だから」と、チコちゃんに答えたいと思います。
経済の好循環のため
日本のGDPの6割は個人消費です。賃金が上がらなければ、消費は伸びません。売り上げの伸びが見込めなければ、企業は新たな投資に踏み出しにくくなります。結果として収益が伸び悩み、賃上げの原資は生まれません。こうした停滞の連鎖が、十三年前の経済政策の大転換まで続いていました。
「どうして賃上げって必要なの?」
それは、経済の好循環のために必要不可欠だからです。賃金が上がれば、消費が増えます。売り上げが拡大するならば、企業は投資に積極的になれます。その投資が企業に収益をもたらし、賃金として従業員に還元されることで、経済は健全に回るようになります。
したがって、皆さんに支払われる賃金こそが、経済を回すエネルギー源であるということを、もう一度よく認識するべきだと思います。
日本は自由で民主的な国ですから、政府が「賃金を上げよ」と命令することはできません。それでも、賃上げによる好循環につながる環境をつくるために、政府にできることは数多くあります。派手さはありませんが、賃上げの重要性を丁寧に訴えながら、実効性のある政策を着実に進めていきます。
本日のタウンニュースに寄稿しました。二宮尊徳翁は「遠きをはかる者は富み、近きをはかる者は貧す」と説いています。「今なすべきこと」に誠実に取り組むとともに、我が国の将来を見据えた政策の実現に努めていきます。
今の議論は減税や補助など「お金を配ること」に偏りすぎており、財源についての関心が薄れています。パイの奪い合いに終始するのではなく、分かち合うための富を生み出す政策を進めていきます。
+++++++++++++++++++
可能性に挑戦し、豊かさを分かち合う社会を
「賃上げ」と「減税」
103万円までの収入に税金がかからない制度は、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法の精神に基づくものだと私は理解しています。
したがって、物価の上昇により基本的な生活費が上がったことに対応して免税基準を引き上げ、実質的な「減税」をすることには大きな意義があると思います。
一方、私は10年以上前から「賃上げ」の必要性を訴えてきました。
日本は独裁国家ではないので、政府、ましてや一人の政治家が企業に対して「賃金を上げろ」と命令することは出来ません。しかし、「賃上げは企業の社会的責任である」と国会で強く働きかけるとともに、賃上げを促進する税制改正も行なってきました。
現在、賃金が上がりつつある状況が続いています。この流れを定着させるために、引き続きしっかりと支援していきます。
そのお金はどこから?
さて、賃金が上がっても、減税を行なっても、皆さんの手元に入るお金が増えるという点では同じです。
また、高校授業料の無償化、幼児教育・保育の無償化、出産費用の助成、福祉タクシー券やバス無料パスなどによっても皆さんの支出が抑えられますから、手元に残るおカネはやはり増えます。
ただ、賃上げとこれらの政策には、大きな違いがあります。賃上げは、経済活動を活発化させて企業収益が上がったことで増えたパイを、従業員の皆さんで分けるということです。
それに対して「無償化」とは「税金によって全額負担しますよ」ということですし、「助成」とは「税金で一部を補助しますよ」ということですから、元手となるのは我々が払う税金です。
財源に責任を
たしかに、ここ数年税収は増えていますが、国債などの政府の借金の残高は昨年末で約1318兆円でした。日本国内で生み出された「稼ぎ」とでもいうべき名目GDPは約609兆円ですから、すでに稼いでいる額の二倍以上の借金があることになります。
したがって、これらの政策を実行するには、どこかから財源を確保してこなければなりません。いわゆるパイの奪い合いです。財源が不足すれば、さらに借金を増やすことになりますが、それでは将来の大規模な財政出動に対応する余力が失われてしまいます。
「借金は悪」「財政赤字は解消すべき」と単純に言うつもりはありません。私が政治家として大切にしているのは、「本当に支援が必要な人のためには、国は借金をしてでも手を差し伸べるべきである」という考え方です。
しかし、今の議論は減税や補助など「お金を配ること」に偏りすぎており、財源の確保についての関心が薄れているように感じられます。私は20年以上のビジネス経験を通じて、「お金は天から降ってこない」ということを学びました。その視点から見ると、現状には危うさを感じざるを得ません。
日本を前へ
政府には、収益を上げて税金を払う能力がありません。しかし、払っていただいた税金を使ってインフラを整備したり、国民の皆さんにとってプラスになる事業を支援したりすることは出来ます。
例えば、桐蔭横浜大学の宮坂教授が発明した薄くて曲がる「ペロブスカイト太陽電池」は、日本が世界第二位の生産量を誇るヨウ素を主原料としています。エネルギーの約九割を海外に依存する我が国にとって、次世代太陽電池を国産の原料で製造できることは朗報です。
また、国際医療福祉大学大学院の下川副大学院長が取り組んでいる世界初の「認知症に対する超音波治療」は、すでに治験段階に入っています。実用化されれば、5500万人と言われる世界の認知症患者を救うことになります。
さらに、私自身が財務金融部会長として抜本的な改革を進めた新NISAは現在2560〇万口座。成人の四人に一人にまで普及しました。これは多くの方の堅実な資産運用を後押しすると同時に、資本市場の成長と安定を通じてスタートアップ企業の資金調達を支援することにもつながります。
立ち止まってパイを奪い合うのではなく、国民の皆さんが前に進むことを支援し、日本の発展を後押ししていきます。


スライドショーはこちらから
本日、神奈川3区内の主要な新聞に折り込みました。「強い経済で、優しい社会を。」そして何と言っても、皆さんの生命と財産を守るのが政治家の使命です。
「足腰の強い経済」という土台があってこそ、皆さんの生命を守り、生活を支え、子どもにもご高齢の方にも優しい社会を作ることが出来ます。引き続き、しっかりとした政策の実現に取り組んでいきます。
-1-500x354.png)
-2-500x354.png)
今朝の駅頭から、新しいチラシになりました。テーマは「憲法改正」です。空理空論ではなく、我々が置かれている現状をしっかりと認識した上で、憲法審査会の委員として冷静な議論を進めていきます。
#中西けんじを応援 #鶴見区 #神奈川区
+++++++++++++++++++++
冷静な議論を ―憲法改正―
厳しい現実
ロシアは、国際法と国連憲章を無視して、今日この時間もウクライナに攻め込んでいます。台湾有事に関して「日本の民衆が火の中に」と、中国大使が我々の目の前で発言したことはご存知の通りです。その中国は、この10年で軍事力を何倍にも強化しました。長距離ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮が核武装を進めていることは間違いありません。日本は不穏な軍事大国に囲まれています。
大切なのは外交努力と抑止力
こうした中、まず優先されるべきなのが、外交努力であることは言うまでもありません。わが国は戦後一貫して平和国家として歩んできました。法の支配を尊重し、いかなる紛争も力の行使ではなく平和的・外交的に解決すべきであるとの方針を変えるべきではありません。
しかし、今の日本が置かれている状況を冷静に考えると、皆さんの命や暮らしを守り抜くために「自分の国を自分で守る」ための抑止力を高めていく、つまり相手に対して「日本を攻めても目標を達成できない」「三倍返しにあってしまう」と思わせることが必要です。
ところが、私たちが大切に護ってきた憲法が、その努力の妨げとなってしまっています。
「戦争放棄規定」は当たり前
第一次世界大戦の悲惨な体験を経て、世界各国は国際連盟を作った上で、「紛争解決の手段として戦争を放棄する」とした「パリ不戦条約」を結びました。したがって現在でも150近い国の憲法に、「平和条項」が盛り込まれています。
しかし、当時63か国がこの「不戦条約」を結んでいたにも拘らず、さらに大規模な第二次世界大戦が起きてしまいました。
「平和を愛する諸国民を信頼」したいのですが
それでも、戦勝国も敗戦国も「もう二度と戦争はしたくない」という気持ちが、強まることはあっても弱くなることはありませんでした。
そこで、新たに定められた日本国憲法では、「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼」するので、戦力は持たず戦わないという形で「パリ不戦条約」の理想を改めて掲げた訳です。これには、「新たに出来た国際連合の集団安全保障によって、世界の平和が守られる」ことが大前提となっていました。
ところが、その国連安全保障理事会の常任理事国ロシアが、ウクライナに武力で攻め込んでいる訳ですから、現実はまだまだ不戦条約の理想とはほど遠いところにあります。
したがって「第9条があるから平和が保たれる」という考え方は、空想的平和主義と言わざるを得ません。哲学者の田中美知太郎京都大学名誉教授は、皮肉を込めてこう言いました。
「平和憲法で平和が保てるのなら、台風の日本上陸禁止も憲法に書いてもらえば安心して寝られる」
解釈改憲では無理があります
憲法を改正するには、非常に高いハードルがあります。そこで、苦肉の策として考え出されたのが「自衛のための必要最小限度の武力を持つことは、憲法上許されると解釈している」という解釈改憲です。
しかし、憲法学者の7割が憲法違反だと言い、どの教科書にも「政府は違憲ではないと言っているが、憲法上の問題があるという意見がある」と書かれています。
この状態のままで「非常時には命をかけて国民を守ってください」というのは、あまりに理不尽です。その場しのぎの解釈ではなく、自衛隊を憲法の中できちんと位置付けるべきです。
占領下の基本法(憲法)を廃止したドイツ
ドイツは占領が終わると、占領国が決めた基本法(憲法)を廃止して新憲法を作りました。というのも、国際法(ハーグ陸戦協定)では、占領が終わった後にまで有効な憲法を定めることが許されていないからです。そして基本法(憲法)の第11条に「侵略戦争の遂行を準備する行為は違憲である」と明記した上で、1955年から正式に再軍備を開始しました。
一方、今の日本国憲法は「新憲法」を定めたのではなく、「明治憲法の改正版」という体裁がとられました。しかし、完全に違う内容になっていますから、これは「国際法違反」という批判を避けるための目くらましです。
憲法を「護る」ということ
憲法を護るということは、条文に指一本触れさせないということではなく、最高法規としての役割を果たすことを護るということだと思います。
「現実と合っていないよ」「憲法にはそう書いてあるんだけどね」などとなると、国民の皆さんにとっての憲法は「護るべき最高法規」ではなくなってしまいます。
現実と乖離している点をきちんと改めていくことこそが、本当の意味で「憲法を護る」ということではないでしょうか。
今朝の投稿でお知らせした通り、今日から新しいチラシになりました。「強い経済で、優しい社会を」
政治は民間企業や個人が活動しやすくするために規制改革や環境整備をします。経済活動が活発になり税収が増えることで、医療や介護、子育てをはじめとした皆さんの暮らしをより良いものにするための政策を推し進めることができます。
++++++++++++++++++++
強い経済で、優しい社会を。
「タフでなければ生きていけない。優しくなければ生きている資格がない」という有名なセリフがありますが、私は「経済が強くなければ生きていけない。皆さんの暮らしに優しくなければ生きている資格がない」と思っています。だから、「強い経済で、優しい社会を」です。
シン・NISAスタート
日経平均が34年ぶりに最高値を更新した要因のひとつとして、「NISAの大幅な拡充」を専門家がこぞって挙げています。
「中途半端な改正ではなくインパクトのある大改革を行なわなければ、いつまで経っても『NISAって何?』のままだ」
「巨大な個人資産の山が眠り続けていては、誰も幸せにならない」
と、自民党の財務金融部会長として制度の抜本的な見直しと大幅な拡充を実現しただけに、相場の大きな節目に何とか間に合ったと少しほっとしています。
海の色が変わった
ただ、国際金融市場で20年以上も「市場」と格闘した経験があるので、「上がった。上がった」と能天気に喜ぶつもりはありません。相場には、上げもあれば下げもあります。
とはいうものの、株式の専門家の間で「株価には『名目の経済活動』に連動する性質がある」という見方が有力であることも確かです。これは「デフレ脱却」という変化が本物であれば、長期的には株価にとってプラスであるということです。私が「恒久化」を強く主張したのは、堅実な長期投資をしっかりと支え続ける制度にしたかったからです。
日経平均の最高値更新は、「相場の潮目が変わった」といった流れの変化の話には留まりません。長年のデフレ脱却に向けた努力によって、株式市場という「海の色が変わった」ということだと思います。
皆さんのためのNISA
NISAに対して「国民の資産を海外に流出させているだけだ」という批判があることは承知しています。「オルカン」と呼ばれる「日本を含む世界中の株式に投資する商品」の売れ行きが好調ですから、「流出」していることは間違いありません。私自身は「日本の企業に投資をして欲しい」と思っているので、とても残念です。
しかし、「資産運用立国」は日本の企業や政府、ましてや金融業者のためではなく、国民の皆さんのための政策です。「日本だけではなく世界に投資したい」と考えた皆さんが「オルカン」などを選べない制度にするのは間違っていると思い、「投資先は日本株のみ」などという制限は設けませんでした。
「日本」の商品の充実を
むしろ、私自身は「日本株関連の商品の品ぞろえが足りていない」と感じています。また、オルカンのような「インデックス・ファンド」に、プロが積極的に運用する「アクティブ・ファンド」が勝てないという考え方にも、必ずしも賛成していません。
投資にあたって取れるリスクは、ひとりひとり違っています。皆さんが投資先や投資手法を自由に選ぶことが出来るのが本当の「資産運用立国」であり、その手助けのためにNISAという制度があると考えていただきたいと思います。
「賃上げ」を訴え続けて八年
日本の家計の金融資産のうち、株式と投資信託の割合は合わせて約15%です。証券口座の開設が急増しているので、これからは増えると思いますが時間がかかります。したがって、経済の好循環には「賃上げ」が絶対に必要です。
国会で「過去最高益を叩きだした企業の労働組合が、ベアの要求を見送るとは何事か」と、経営者も組合もデフレマインドに憑りつかれていること指摘したのは2016年でした。ただ、わが国は自由主義国家ですので、私企業の賃金に政府が直接口を挟むことは出来ません。その後も再三再四取り上げて税制面から後押しをしてきましたが、結果は芳しくありませんでした。
「空気」を変えよう
しかし、あきらめてはいません。山本七平氏の「空気の研究」にある通り、わが国では「空気」が大きな役割を果たしてきています。そこで、「コーポレートガバナンス・コードの中に、『従業員との対話だけを担当する取締役を置く』と定めて、ステークホルダーとしての従業員の権利を明示すべきである」という突っ込んだ提案を改めて国会で行ないました。「賃上げが必要」という空気を、さらに大きくしていきたいと思います。
気持ちも新たに、今朝の駅頭から「TEAM鶴見」と「TEAM神奈川」のチラシをお配りしています。皆さんの生活をより良いものとするために、市・県・国が一体となって頑張ります。
++++++++++++++++++
NISA(少額投資非課税制度)の大改革
「毎月『つみたてる』というのに年間枠が40万円。12で割り切れない今の制度はおかしい」などと漫才のようなツッコミも交えて、国会でNISAの思い切った改善を訴えたのは3年前のことです。
昨年の8月に政策の立案に深く関わることが出来る自民党の財務金融部会長となってからは、さらにギアを一段と上げて「中途半端な改正ではダメ。『資産所得倍増』の名にふさわしいものにするべきである」と走り回りました。
それだけに大手のメディアだけではなく、インターネット上で自由に発言をする皆さんからも高い評価をいただき、「これだけのきちんとした制度が出来たのならば、コツコツと投資を始めてみようと思う」という声が聞かれるようになったことは喜びに堪えません。
物価が上がらない時には、現金を壺にでも入れて床の下に置いておくのが正しいやり方でした。しかし、インフレになれば目減りしてしまいますから、制度の大改革は何とか間に合ったと思います。
つみたてNISAは40万円から3倍の120万円へ、「成長投資枠(元の一般NISA)」は120万円から2倍の240万円へ、さらに両方の制度を併せて利用することが出来るようになったので、年間投資枠が合計で360万円へと非常に大きくなりました。
しかも、制度は恒久化つまり無期限です。もう一つ付け加えると、1800万円という限度額の枠の中で何度でも利用出来るので大変使いやすくなりました。
投資について考えてみましょう
値動きのあるものに投資をする訳ですからリスクはあります。しかし、リスクは避けるべきものでもなければ悪いものでもなく、勇気を持って挑むべきものだと思います。また、長期の株式投資には、社会の役に立つ事業を行なっている企業を応援するという意味もあります。
そんな難しい話をしなくても、「製品やサービスに魅力を感じているから」と株を買った会社が、さらにワクワクするようなものを世に送り出すのを見るのは、応援している選手がホームランを打つような楽しさがありますね。
日本経済が変わる
日本経済を取り巻く状況は、明らかに変わり始めています。37年前に暴力的に襲って来て居座った円高によって、優秀な技術と製品を持った企業でも海外に出て行かざるを得ませんでした。しかし、金融政策が大きく変わって10年が経ち、極端な円高の恐怖が無くなったことから有力な企業が日本に戻りつつあります。
また、海外から日本への直接投資も増加し始めました。これは「日本にチャンスがある」と見る人が増えたことを示しています。
GDPで見ると低成長が続いているのに国の税収が過去最高になっているということは、収益が上がっている企業が沢山あるということです。その恩恵を皆さんが受けるには、まずは賃上げです。ただ、株式を持っていれば、配当や値上がりによる利益も得られることになります。そういう良い環境を作っていきたいと思います。

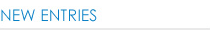
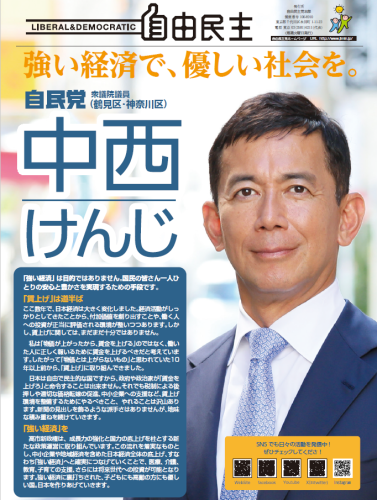










-1-500x354.png)
-2-500x354.png)






