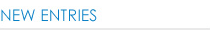文字サイズの変更
- 小
- 中
- 大
挑戦するということ
-トライアスロン-
鉄人という夢
水泳と自転車のロードレース、さらには長距離走をいっぺんにやるトライアスロンは、「鉄人レース」と呼ばれることもある大変過酷なスポーツです。そのために「いつかはトライアスロン」と思ってはいたものの、その「いつか」がやってくることはなかなかありませんでした。
ネックになっていたのは水泳です。「かけっこをやったことのある人」と聞けば、ほぼ全員の手が上がると思います。しかし「何十メートルも必死に競争して泳いだ経験のある人」となるとどうでしょう。私にもそんなことをした記憶はありませんでしたから、一斉にスタートして押し合いへし合いして泳いでいる選手の中にいる自分を想像することは出来ませんでした。
挑戦
その日がやってきたのは50歳を過ぎてからです。20年以上勤めた会社を辞めて、政治の世界に飛び込むことは大きな挑戦でした。そのことが、私の体のスイッチを入れたのかもしれません。「いつまでも夢のままではいけない」と競技用の自転車を買って大会に申し込みました。
海を泳ぎ、自転車を漕ぎ、最後に走る。3つの競技それぞれについて十分な練習をしなければゴールにたどり着くことは出来ません。当然ですが多くの時間がかかります。「ビジネスの世界で叩き込まれた時間管理を問われているのだ」と自分に言い聞かせながら、夢の実現に向けてひたすら泳ぎ、漕ぎ、走りました。
過酷なレース
最初の大会は、やはり大変でした。集団になっていますから、腕が当たったり足で蹴られたりしてスムーズに泳げません。これは「障害物競泳」という新種目です。まさか、ぶつかりながら泳ぐ練習が必要だったとは思いもしませんでした。
自転車に乗ってからも、やはり集団での競り合いが続きます。しかも今度は猛スピードで走っている最中の接触ですから、常に転倒の危険を感じていました。最後は長距離走。ホノルル・マラソンを完走した経験はあるものの、泳いだ上に自転車で筋力を使っているので体の状態が全然違います。思うように足が動かなくなったのですが、何とか完走しました。
その後、様々な大会に出場してきました。過酷なスポーツであるだけにゴールした後の喜びはひとしおです。大げさにいえば「自分は生きているんだ」という実感、生命力のようなものを感じます。そうした充実感が、このスポーツ最大の魅力なのだと思います。
挑戦するということ
「何故つらい思いをするトライアスロンに挑戦するの?」と聞かれると、イギリスの伝説的な登山家ジョージ・マロリーの言葉を思い出します。
1923年。まだ誰も登頂に成功していなかったエベレストに、3度目の挑戦をする前年のことです。記者から「何故あなたは登るのか?」と聞かれたマロリーは「そこにエベレストあるから(Because it’s there.)」と答えました。
マロリーにとっては、「挑戦を続けること」「登山家として山に登り続けること」自体に大きな価値があったのだと思います。すでにその視線は、世界一高い山の頂上よりもずっと先にあったのかもしれません。
政治家の使命は、一つでも多くの課題を解決すること。課題に挑戦を続けることです。皆さんの暮らしをより良いものにするという目標には、頂上もゴールもありません。その先を見据えて、これからも泳ぎ、漕ぎ、そして走り続けていきます。

昨日の会議の内容が詳しく報じられています。座長としてスピード感を持って取り組んでいきます。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61030800R00C20A7PP8000/
月刊誌Wedge 2015年5月号「企業価値4兆円超!『破壊者』UBERの正体」のなかで、旅館業法の規制緩和(Airbnbの活用など)への取り組みが掲載されました。
Wedgeの特集は、AirbnbやUBERといった新しいアイディアによるビジネスモデルと、旧態依然とした法規制との軋轢に焦点を当てたものです。そのなかで、「旅館業法の規制を緩和し、空き家の有効活用を図るべきだ」という主張が採り上げられました。
Airbnbとは、個人が、個人所有のマンションや別荘を宿泊施設として提供するに当たり、インターネットを通じて仲介を支援するサービスのことです。
Airbnbの活用が進み、当面使う予定のないマンションや別荘の宿泊施設としての提供が増えれば、今後予想される宿泊施設の不足(訪日外国人旅行者2000万人・3000万人時代に予想される宿泊施設の供給不足)の有効な解決策になると考えられます。
のみならず、昨今問題視されている空き家の活用にもつながり、空き家問題をビジネスチャンスに変えることも不可能ではありません。
もっとも、個人宅の宿泊施設としての提供に問題がないわけではありません。
なぜなら、頻度・態様によっては、「人を宿泊させる営業」として旅館業法の規制が及ぶ恐れがあるからです。仮に、旅館業法の規制が及ぶとすれば、客室数や床面積の基準、水道水などの衛生基準を満たした上で、旅館営業の許可を受ける必要があります。
そのため、Airbnbを通じた日本国内の宿泊施設の提供は、旅館営業の許可を受けない限り、旅館業法に抵触する恐れのあるグレーゾーンで行われているのが実態です。
この点について、Airbnb運営者は、利用者(宿泊施設の提供者)に対して、旅館業法の許可を受けるように求めていますが、現実的ではありません。
確かに、Airbnbのビジネスモデルは優れたものですが、現在のグレーゾーンな環境での運営は、旅館業法の規制のお目こぼしに基づく「裏街道」でしかありません。
真っ当なビジネスモデルとして「表街道」で堂々と競争するためには、Airbnb運営者の側も、利用者(宿泊施設の提供者)に責任を転嫁するような運営を改め、正々堂々と規制緩和を訴える姿勢が必要なのではないでしょうか。
Wedgeにも以下の見出しが掲載されています。
「裏街道」に健全な発展なし
「表街道」で堂々と競争できる環境を
技術の進展や環境の変化に応じた規制緩和を求めていく中で、その時代に応じた適切な規制が導かれていくのではないでしょうか。
今後も、Airbnbのような新しいビジネスモデルを積極的に支援して参りたいと思いますが、事業者にも「表街道」を正々堂々と歩む覚悟を求めてまいりたいと思います。
【参照】3/17(火)参議院 予算委員会報告③ 旅館業法の規制緩和
http://nakanishikenji.jp/diet/15149
【参照】質問主意書≪旅館業法≫