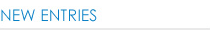文字サイズの変更
- 小
- 中
- 大
「金融緩和策の本丸と言えば金利です。現在、銀行などが日銀に預けている超過準備に対しては、+0.1%の金利が付けられています。昨今の経済状況を考えると、これを『ゼロにする。または引き下げる』と言うカードを切るべきではありませんか?」
「いわゆる付利金利の引下げということについて、検討は致しておりません」
これは今国会の冒頭、1月18日の参議院予算委員会での黒田日銀総裁と私とのやりとりです(http://nakanishikenji.jp/diet/16899)。このわずか11日後の政策決定会合で、日銀は「ゼロ金利」を通り越して「マイナス金利」政策の採用を決定しました。「検討は致しておりません」と答弁したものの、内心穏やかではなかったはずです。
私は、「経済の収縮とデフレの悪循環を断ち切る為に、大胆な金融緩和を行なうべきだ。非伝統的な手段をとる事を躊躇してはならない」と一貫して訴えて来ました。
金融市場の関係者にとって、非伝統的な手段とは邪道以外の何ものでもありません。しかし、デフレと言う泥沼にはまってしまった以上、あえて「人跡未踏の地」へと進む勇気を政策当局者に求めました。
黒田現総裁が就任した事で、日銀はこの「異次元」の世界にようやく足を踏み入れました。就任早々のバズーカ緩和、その後のサプライズ緩和などと呼ばれる非伝統的な手段が講じられた事で、失業者が減少し企業業績も急激に回復、デフレマインドの払しょくにも遂に成功したかに見えました。
しかし、原油価格の暴落と言う思わぬ伏兵に襲われた事で、雲行きが怪しくなっています。2014年6月頃のピーク時に110ドル近かった原油価格は、わずか1年半程の間にほぼ四分の一である30ドルを割れる水準にまで下がりました。
狂乱物価を引き起こした第一次石油ショックの時が3ドルから11.5ドルへと四倍弱でしたから、まさに「逆石油ショック」と言っても良い状態です。
昨年の初めに50ドルを割り込んだ時点で、「2年をめどに2%」と言う物価上昇目標の達成が不可能であることは誰の目にも明らかでした。その後夏場にかけて60ドル台に近付く場面があったものの、年末にかけては逆に大きく下がってしまいました。
そこで国会での審議を通じて一層の緩和策を求めたのですが、日銀は「食料とエネルギーを除けば」「生鮮食品とエネルギーを除けば」と言った新しい基準を持ち出し、「物価の基調は依然としてしっかりしており追加緩和は必要ない」と言う姿勢を崩しませんでした。
ただ「情勢が大きく変化したにも関わらず、旧来の姿勢に固執している」と見られるのは、政策当局者として好ましい事ではありません。
事実、昨年秋頃からは「日銀は市場の前を走る事をやめた」「後追いで対応する姿勢に変わった」「資産買い入れは限界」「もはや手詰まり」などと囁かれ、市場関係者の間では「総裁の言う『必要とあらばいつでも緩和する』の『必要な時』は、永遠にやってこない」と言われる様になっていました。「中央銀行に対する信認の低下」と言う、もっとも警戒すべき事態が迫っていました。
たとえば、昨年12月の「補完措置の導入」は、本来もっと評価されてしかるべきものです。この措置は、日銀自身が「追加緩和ではない」としていたとは言え、「この先追加緩和を行なうに当たって、事前に解決しておくべき技術的な問題」にきちんと対応したものでした。
しかし、市場が「強い失望感」を示し、国民の間に不安感が広がった事はご記憶にある通りです。一度下がってしまった信認を取り戻すのは、容易な事ではありません。
そんな中、世界の金融市場は、年初から大荒れになりました。もはや一刻の猶予もなりません。「本丸である金利に、手をつけるべき時が来ているのでは?」と言う問いを黒田日銀総裁に投げかけた背景には、この様な強い危機感がありました。
今回の日銀の金融政策の変更は、単なる追加緩和ではありません。従来の「量的・質的金融緩和」と言う枠組みが大幅に変更され、より強力になったと大いに評価すべきものです。従来の「量的」金融緩和とは、大量の国債を購入して市中のマネーの量をコントロールする政策でした。「質的」金融緩和とは、ETFやJ-REITなどと言った国債以外の資産も購入すると言う政策です。
これに「金利のコントロール」と言う武器が、新たに加わりました。この結果、「金融緩和策の行き止まり感」の払しょくに成功しています。
今回日銀が採用したシステムには、諸外国の政策担当者からも評価する声が上がっています。若干技術的な話ですが、すでにマイナス金利政策をとっている諸外国は、「プラスとマイナス」の二階層システムを採用しています。それに対して、日銀が「ゼロ」を加えた三階層とした事で、「マイナス金利政策の自由度が高くなった」と評価する声が高いと言う事です。
これまでは、「金利をゼロ以下に下げる事は出来ない」と言ういわゆる「ゼロ金利制約」と言う事が強く意識されてきました。しかし、今後はこの金融政策の「ゼロ金利制約」は、非常に小さくなります。
また「マイナス金利」と聞くと、日頃金融市場との関わりが薄い人でも「おや?」と思うはずです。2%と言う物価目標の達成に対する強いコミットメントを、改めて印象付けるのに成功した事は間違いありません。これはインフレ・ターゲット政策を遂行する上で、非常に重要です。
これまでの「資産買い入れ額の増額」だけではなく、「マイナス金利幅の拡大」と言う武器を持った日銀の金融政策によって、デフレからの脱却の道筋が確固たるものとなると大いに期待したいところです。
私が再三求めていた大胆な金融緩和政策は、黒田日銀総裁のいわゆるバズーカ緩和とそれに続くサプライズ緩和と言う形で実現されました。また、国内の総供給に対して総需要が足りない時(需給ギャップがある時)に財政出動を行なった事も、基本的には正しい経済政策であったと考えています。その結果、雇用情勢や企業収益などに、明るさが見えてきていたのは確かです。
ところが、消費税率が5%から8%へと引き上げられた事で、歯車が狂ってしまいました。私は消費増税自体が悪だとは考えていません。しかし、「賃金の上昇が始まる前の増税は、病み上がりの患者に冷水を浴びせかける様なものだ」として反対していました。結果は危惧していた通りです。これを「予想を超えた悪影響」などと、あたかも降ってわいた天災の様に呼ぶのはおかしなことです。
ただ、この消費増税の悪影響がなかったとしても、果たして日本経済が活力を取り戻せていたかというと疑問です。財政政策や金融政策は、景気を刺激し下支えしてくれます。しかし、経済の潜在成長力、つまり長期的に成長する力をつけてくれる訳ではありません。
そこですぐに思い浮かぶのはアベノミクスの三本目の矢、しかも「本丸」として挙げられていた「成長戦略」です。ただ、金融・財政政策と言う一本目と二本目の矢と比べると、その内容が判然としません。
「規制緩和等によって、民間企業や個人が真の実力を発揮できる社会へ」と言う方向性は分かっても、具体的な話となると一向に見えてきません。国家戦略特区を定めて、医療、雇用、農業などの分野で、既得権益に守られた「岩盤規制」を地域限定で緩和しようとしていますが、日本全体の成長につながるまでにはまだまだ時間がかかります。
そんな中、あまり注目されていませんが、反成長戦略とでも言うべき状況が、日本全体に温存されている事は深刻な問題だと考えています。
中小企業金融円滑化法は、2013年3月31日に期限切れとなりました。そろそろ3年が経とうとしていますので、皆さんのご記憶からは消え始めていると思います。この法律の延長が提案されるたびに私は反対をしてきましたので、「ようやく廃止された」と言う思いです。
ところが、期限切れとなった後も、金融庁の指導により「貸し付け条件の変更」つまり返済猶予が続けられてしまっています。
この法律が導入されたのは、リーマン・ショック直後の2009年12月です。たしかに、当時の急激な経済情勢悪化に対する緩和策としては有効な薬でした。しかし、その一方で「経済の新陳代謝を停止させる」という副作用を持っていたことも間違いありません。
たとえ稼ぐ力がなくなった企業であっても、従業員の雇用を守っている限り社会に貢献しているという考え方もあります。また、既存の企業が技術革新を行い、経営改革を通じて生産性を向上させていけば良いではないかと言う考え方もあります。
しかし、経済全体の成長や生産性の向上をはかる為には、新たな活力を持った優れた企業が参入し、非効率な企業が退出するという新陳代謝が不可欠です。稼げなくなった企業からヒト、モノ、カネが放出されなければ、新たに参入したい企業に、この経営に不可欠な三要素が回ってくることはありません。
どの先進国においても、新たに開業する企業(開業率)と廃業する企業(廃業率)とはほぼ均衡しています。たとえばアメリカは9.3%/10.3%、ドイツは8.5%/8.1%、フランスは15.3%/11.1%、イギリスは14.1%/9.7%です。日本はと言えば、均衡してはいるのですが4.8%/4.0%と著しく低い水準にあります。
開業率が低いことから、「日本人にはベンチャー精神が欠けている」などと言われます。しかし、実は「退出して経営資源を放出してくれる企業が少ない」事にも、大きな問題があると思われます。資源配分が適正に行われなければ、経済が真に活性化することはありません。
雇用の流動化には痛みが伴います。しかし、現在返済猶予を受けている30万社とも40万社とも言われる企業の内、健全性を取り戻す企業は1割もないとされています。返済猶予や「追い貸し」で延命している再建の見込みが薄い企業にいたのでは、賃上げはおろか前向きに働く喜びすら怪しいものとなってしまいます。
短期的には救われている様に見えても、長期的に不幸な状態に陥る事は避けねばなりません。もちろん、再雇用を円滑にする為の再教育制度の拡充、職場が変わっても引き継げる社会保障制度体系の構築、医療や年金制度の雇用形態による差別の撤廃など課題はあります。
しかし、痛みを避ける為に金融機関に延命治療をさせ続けるのは、ジリ貧を恐れてドカ貧に陥る道です。これからの国会での審議の中で、この様な「反成長戦略」が目に見えないところで続けられている事を指摘し、改善を求めていきたいと考えています。