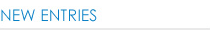文字サイズの変更
- 小
- 中
- 大
〇中西委員
皆さん、おはようございます。自由民主党の中西健治でございます。
世界中、そして日本も含めて大変な状況になっております。今日は日銀総裁にお出ましいただいておりますけれども、いま一度、この局面において、日本銀行の金融政策について整理を少し試みたいというふうに思っております。日銀総裁には分かりやすい答弁をお願いしたいと思います。
まず、これまでの金融調節、引締めについて、その理由をお伺いしたいと思っています。
三月の政策決定会合の主な意見では、物価に関して、ほぼ全員がインフレ目標達成への自信の高まりを示しており、そのうち約半数がインフレの上振れリスクを指摘しておりました。さらに、総裁自身、先月、三月二十六日の当委員会で、現在の実質金利は極めて低い水準にあるとの認識を示しておられます。
実質金利が極めて低く、インフレに上振れリスクがあるのであれば、当然、利上げを急がないといけない、こういうことになるかと思いますが、今の日銀にはその気配は感じられません。
さらに、政策決定会合の要旨を見ても、記者会見などでの発言を聞いても、総裁は、インフレを退治するために利上げをしたとか、インフレ退治のために利上げを続けるなどとは一言もおっしゃっていません。むしろ、データがオントラックに推移すれば利上げする、こういう物の言い方をされております。
したがって、今の利上げ局面は、あくまで金融政策の正常化を目的としたものではないかと思われますけれども、この点について総裁に伺いたいと思います。
○植田参考人
お答えいたします。
私ども、基本的には、二%の物価安定目標を持続的、安定的に実現するという観点から政策を運営してまいります。長期的な物価の動向に関係が深い基調的な物価上昇率というものを注意して見ておりますが、これは二%に向けて徐々に高まってきているということを確認する中で、昨年三月以来、何回かの政策金利の引上げを実行してきたところでございます。これは、繰り返しになりますが、物価安定目標を持続的、安定的に実現するという観点で行ってきた政策変更でございます。
○中西委員
正常化というようなことについて今全くお答えをいただいていないわけでありますけれども、普通、多くの中央銀行というのは、金融政策を使って経済に働きかける、こういうことをするわけですけれども、総裁の、経済がオントラックであれば利上げするというのは、やはり金融調節を目的としているというふうに思わざるを得ないというふうに私自身は考えております。
ただ、私は、この金融の正常化ということ、これ自体は否定されるべきものではないだろう、いざという事態が生じたときに金融調節ができる柔軟性、これを確保するということは極めて重要だというふうに思っております。
総裁は就任以来、私は、順序立てて、非伝統的金融政策を排して利上げを行ってきている、こういうふうに考えておりますので、これは私は、政策をいざというときに発動できる柔軟性を確保するということも、日銀のこれまでの政策決定の中で大きな理由になっているのではないかと思いますが、この点、いかがでしょうか。
○植田参考人
やや繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、私どもは、ここまで金利を少しずつ引き上げてきた背景といたしましては、経済、物価情勢が改善する下で低金利を継続しますと、金融緩和の度合いが過大なものとなるおそれがありまして、場合によっては物価上昇率が加速する、後になって急速な金利の引上げを迫られてしまう、こういうリスクもある。
こうした状態を回避しつつ、経済、物価情勢に応じて適切に政策を運営していくことが、物価の安定を通じて息の長い成長を実現していくことにつながり、国民経済全体にメリットを及ぼすというふうに考えてきたところでございます。
○中西委員
物価が思わぬ上昇を将来するのかもしれない、それを予防的に、ないようにする、そうしたことも一つの重要な政策目的だろうというふうに思いますが、やはり金融の正常化ということも大変大きな目的ではないかというふうに思います。
FRBの元議長、バーナンキさんが、量的緩和政策については、理論的には効果がないが実際には利いた、こういうふうなことを言っております。それは、異次元の政策を取ったわけですから、この異次元の政策というのは理論的に説明できるものでもない、こんなようなことを言っていらっしゃるわけですけれども、今もまだ日銀は、量的緩和を縮小しつつありますけれども、やはり異次元にいるのだろうというふうに思いますので、そこから普通の正常な世界に戻るために、私は金融政策を今まで引き締めてきているんだろうというふうに思います。
それで、今回のトランプ・ショックであります。新たな事態が起きたということではないかと思います。
多くの方が大恐慌のさなかに、一九三〇年、アメリカではスムート・ホーリー法というのが制定されましたけれども、平均関税率が四〇%に引き上げられたということがございました。そして、大恐慌は更に長引くということになりました。今のトランプ関税というのは、この一九三〇年のことを考えると、先祖返りしたにすぎないのではないか、こういうふうに思えるところがございます。
ということは、トランプの数年間、四年間かもしれません、四年間だと思いますけれども、経ても、アメリカはこの政策を取り続ける、先祖返りしているわけですから、可能性は否定できないだろうというふうに思います。ですので、大地殻変動が起きている、そして影響が大きく、長く続く可能性があるということなんじゃないかと思います。
これだけのショックが起きてきているので、私は新たな対処すべき事態が日本銀行にとっても生じているのではないかと思いますが、その認識はいかがでしょうか。
○植田参考人
今般の自動車関税あるいは相互関税の導入によって内外の経済、物価をめぐる不確実性は高まったというふうに、もちろん見ております。それがどういう経路を通じて我が国経済、物価に影響を及ぼすかという点については、複数の可能性がございますので、現在、注意深く分析を続けているところであります。
また、関税政策が今後どういう展開をたどるかという点についても、ある程度不確実性がまだ残っているというところでございます。こうした動向を十分に注視しながら、適切に政策運営を進めてまいりたいと思っております。
○中西委員
注意深くですとか注視するということをおっしゃいましたけれども、やはり、もっとはっきりしたメッセージを送らないといけないんじゃないかというふうに私は思っております。
これだけの事態ですから、大変大きな影響、不安心理が人々を覆っている、世界を覆っている、日本を覆っているということなんじゃないかと思います。総裁は金融の正常化ということをおっしゃいませんでしたけれども、私は、これまで金融正常化、まだ続けたかったんだろうけれども、これだけのことが起こってしまったので、これにはしっかり対処していくべきだというふうに考えております。
はっきりしたメッセージということでいうと、大変参考になるのが、ギリシャ・ショック、ユーロの通貨危機、ギリシャ通貨危機のときの、そのときのECBの総裁であったドラギさんの言い方であります。ドラギさんは、そのときに極めてシンプルなメッセージを発しました。それは、「我々の権限の範囲内で、ユーロを守るためには何でもやる用意がある、そうして信じてほしい、それで十分だ」、こういうシンプルで強いメッセージを発しました。そして、これがドラギ・マジックと言われましたけれども、ユーロ危機というのは、通貨危機というのは収束に向かっていったということであります。
やはり、これまで日銀というのは、世界初の、白川さんのとき、黒田さんのとき、いろいろな政策を打ったことは間違いありませんけれども、それが響いたかというと、なかなか響かず時間がかかったということなんじゃないかと思います。やはり、強いメッセージ、クリアなメッセージを日本銀行には出してもらいたい、こういうふうに思います。
こういう危機を、もう危機と呼んでいいと思いますが、迎えて、注視する、注意深くではなくて、あらゆる手段を動員する、そうした用意はございますか。
○植田参考人
関税政策につきましては、先ほど申し上げましたとおり、今後の動向はどうなのか、どう変わっていくのかという点も含めて、残っている不確実性がございます。これを丁寧に見極めつつ、私ども、経済、物価情勢、あるいは市場動向も確認し、見通しをしっかりと持ち、それに応じて適切に政策を判断するという姿勢でございます。
○中西委員
総裁、適時適切を繰り返されてされています、注意深く見守るということもおっしゃっていますけれども、これだけは言いませんか。政府と日銀は歩調を合わせてしっかりと対処していく、日銀総裁、お願いします。
○植田参考人
もとより、私ども日本銀行としましては、政府と緊密に連携しつつ、引き続き、市場動向あるいは経済、物価への影響を十分注視してまいりたいと考えております。
○中西委員
政府は切迫感を持って対処しようとしていますので、きっちりと歩調を合わせて対処していってもらいたいと思います。日銀総裁への質問はこれで終わります。御退席いただいて結構でございます。
○井林委員長 日銀総裁、御退席ください。
○中西委員
続きまして、株式市場は大変なことになっていますが、ちょっとNISAについて金融庁並びに金融担当大臣にお伺いしたいと思います。今、三万三千円、日経平均で昨日は三万三千円ちょっとというところでしたけれども、新しいNISA、去年の一月、新NISAが始まったときの株価は三万三千百九十円でありました。ということは、ちょうどそのレベルに昨日の終わり値あたりではいたということになります。
これからまた一段下がっていくということになると、ああ痛いということになる人も出てきますけれども、実は、一旦は上に上がったのが返ってきている、こういう水準であるということは知っておいていただきたいというふうに思います。その上で、やはり、長期、分散がNISAの制度の意味合いですから、しっかりと長期、分散でまた投資を続けていってほしいなというふうに私自身は思っているところであります。
その中で、このNISAですけれども、長期の運用ですので、元本を取り崩すようなことはしない、利息は、配当はすぐそのまま再投資に向ける、こういう商品が対象となっております。それは意味のあることだろうというふうに思いますが、このNISA、一年終わってみて、やはり若い人の利用率が非常に高いんです。二十代、三十代、四十代、五十代ぐらいまで、三十代、四十代がピークなんですね。そこからだんだん下がってきて、年齢が上に上がると余り関心がなくなっていく、使っていないということになります。それはどういうことかというと、やはり、お年を召してから、積み立ててくれといってもなかなかということなんじゃないかと思います。
そんな中で、今、御高齢の方々、年齢が高い方々に限って、元本を取り崩してもいい毎月分配型の商品というのは、年金は隔月ですから、それの補完をするものとしても大きなニーズがあると思いますが、こうした商品を年齢を限って認めていくというのは、金融担当大臣、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣
御指摘のように、高齢者においても口座数は増加はしているものの、二十代、三十代と比べるとその伸びは小さいと認識をしております。また、これまでも、今おっしゃるような取崩し型というんでしょうかね、分配型に対する御要望というのも頂戴はしていると思いますが、他方で、そうしたものが、これまでもそういった商品があって、それがどうだったのか、特に手数料等々含めていろいろな課題があったということも委員御承知のとおりだろうと思っております。
私どもとしては、まず、そうした商品構成を云々する前に、高齢者においても、長期、積立て、分散なんですけれども、高齢者からいうと長期、積立てはちょっとあれかもしれませんが、分散というのはまだまだありますし、高齢者においても、預貯金の形でかなり高い割合を持っておられますから、そういった意味においても、それぞれの御本人が、これからの人生の中でどういうライフイベントがあって、それに向けてどういう現金が必要だ、どういう流動性を確保しなきゃいけないというようなこともしっかりプランニングしていただいた上で、そうでない部分についてはよりうまく運用していただく、こういったこともしっかり申し上げていくことが必要だ。
そういった意味において、NISAの活用も含めて、金融経済教育、これを通じて、これは若い方だけではなくて高齢者の方も含めて、全般的な展開、これをしっかり努めていきたいと考えています。
○中西委員
質問を終わりますけれども、私は、高齢者向けに、年齢を区切った上で、プラチナNISAみたいなものをつくったらいいだろうというふうに思っております。
どうもありがとうございました。