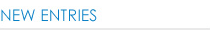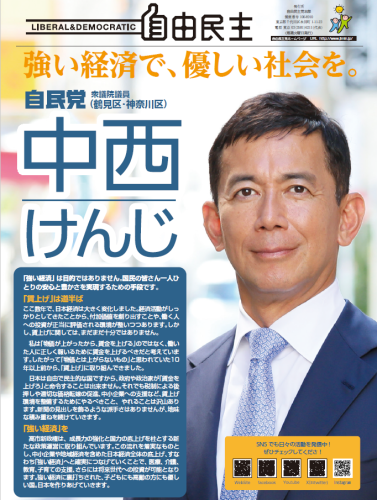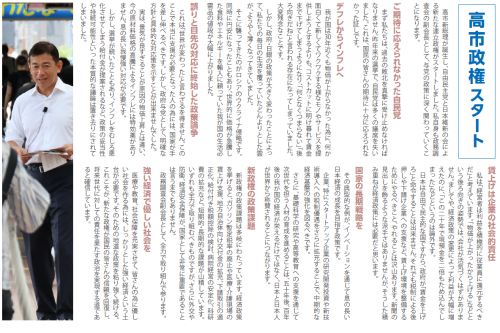文字サイズの変更
- 小
- 中
- 大
日本の人口は減少していますが、神奈川3区は成長を続けています。一方、高齢化は他の地域と同じように進んでいます。この大変難しい政策運営に対して、市、県、国が一体となって取り組んでいきます。#鶴見区 #神奈川区
「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と言われないように、しっかりと取り組んでいきます。
(鶴見区版 https://x.gd/9IhBy)
(神奈川区版 https://x.gd/X1YgL)
#鶴見区 #神奈川区
どうして賃上げって必要なの?
「ボーっと生きてんじゃねーよ!」
チコちゃんに叱られる!の有名なセリフですね。当たり前すぎて理由なんか考えたこともないことについて、改めて 「なぜ?」と問い直されるたびに、「えっ、なんでだっけ?」「確かに考えたことなかった、、、」と、私も答えに窮しています。
そこで「どうして賃上げって必要なの?」とチコちゃんに聞かれたらどう答えるのか考えてみました。
「過去最高益を上げた企業が、賃金を上げないのはおかしい。我が国の企業の労働分配率、つまり会社がもうけたお金のうち、どれくらいを従業員の給料として回しているかを示す割合は、世界的に見て低い状態が続いている。それを、さらに下げてしまうなどということは理解に苦しむ」と国会で取り上げたのは十年も前のことです。
それから何度も「賃上げを、、、」と言い続けてきたので、私にとっては当たり前すぎて、改めて理由を考えたことなどありませんでした。でも、答えに窮している場合ではないですね。
家計や生活の安定のため
すぐに思いつくのは、物価が上がっているのに賃金が上がらないと、買いたいものが買えなくなってしまうということです。
逆に、物価の上昇を上回る賃上げによって安心して暮らせるようになれば、多くの皆さんの気持ちが明るくなります。仕事に対する意欲が高まりますから、さらに頑張ろうという後押しになることは間違いありません。
ということで、答えは「皆さんの生活を守るためだから」になりました。
ただ、これではイマイチですね。「物価が上がったから賃金も上げる」というのでは、まったく後ろ向きです。物足りません。そんな経営者がいたら、本当に「ボーっと生きてんじゃねーよ!」です。
会社が生き残るため
経済活動が活発になってきたので、人手不足を訴える企業が増えました。ブラック企業が社会問題となった時代とは、完全に変わっています。
そんな中で人材を確保するには適切な報酬が不可欠ですから、賃金を上げるのは当たり前ですね。これは生産性の低いビジネスモデルからの転換を促すことにもなり、日本経済の体質の改善につながります。
更に付け加えると、日本の賃金は諸外国と比べて低くなってしまっています。高い付加価値を生む優秀な人材に正当な賃金を払わないと、「だったら、海外に行って働くよ」と言われかねません。人材の流出は、日本の成長力を殺いでしまいます。
そもそも、働く皆さんに対して払う賃金を、コストだと考えるのはおかしなことです。松下幸之助翁は「企業は人なり」と言う名言を残しました。企業は収益を上げるために設備投資や研究開発投資などを行ないますが、実は人材に対する投資が一番大切なものです。
従って、「賃上げは、会社が生き残るために重要な投資だから」と、チコちゃんに答えたいと思います。
経済の好循環のため
日本のGDPの6割は個人消費です。賃金が上がらなければ、消費は伸びません。売り上げの伸びが見込めなければ、企業は新たな投資に踏み出しにくくなります。結果として収益が伸び悩み、賃上げの原資は生まれません。こうした停滞の連鎖が、十三年前の経済政策の大転換まで続いていました。
「どうして賃上げって必要なの?」
それは、経済の好循環のために必要不可欠だからです。賃金が上がれば、消費が増えます。売り上げが拡大するならば、企業は投資に積極的になれます。その投資が企業に収益をもたらし、賃金として従業員に還元されることで、経済は健全に回るようになります。
したがって、皆さんに支払われる賃金こそが、経済を回すエネルギー源であるということを、もう一度よく認識するべきだと思います。
日本は自由で民主的な国ですから、政府が「賃金を上げよ」と命令することはできません。それでも、賃上げによる好循環につながる環境をつくるために、政府にできることは数多くあります。派手さはありませんが、賃上げの重要性を丁寧に訴えながら、実効性のある政策を着実に進めていきます。